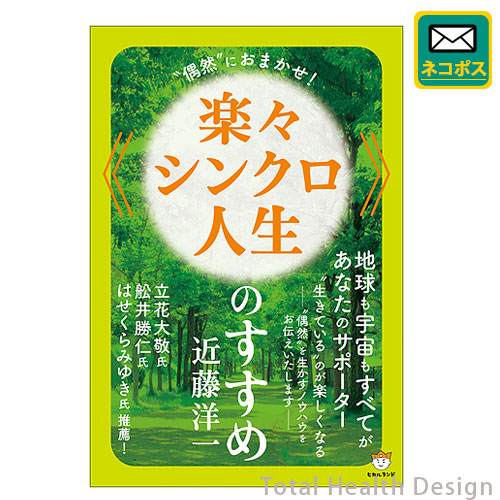2012年10月01日
手作り酵素(2)
前回では、元気で生きていく上で、なくてはならない大切な働きをしてくれている人体常在菌についてご紹介させていただきました。
人の体に常在菌が棲み着いてくれているおかげで、美しく健やかに生きていくことができるのですが、本稿ではもう少し根源にまでさかのぼって考察を進めることにいたします。
人の起源
旧約聖書の冒頭に天地創造の物語が出てきます。いよいよ人の誕生ですが、その模様について次のように記述されています。
……主なる神が地と天とを造られた時、地にはまだ野の木もなく、また野の草も生えていなかった。……主なる神は土のちりで人を造り、命の息をその鼻に吹きいれられた。そこで人は生きた者となった。主なる神は東のかた、エデンにひとつの園を設けて、その造った人をそこに置かれた。また主なる神は、見て美しく、食べるに良いすべての木を土からはえさせ、さらに園の中央に命の木と、善悪を知る木をはえさせられた。
―――聖書によると人の起源は土なのです。
現代科学では、この宇宙はビッグバンから始まったとしています。そして今から45億年ほど前に地球が誕生し、それから10億年程経過して、海の中にはじめての生物が誕生したとしています。やがて陸上には植物が繁茂し、人間の誕生につながっていくのですが、植物も動物もそして人間も原材料は土ということになります。
日本にも“身土不二(しんどふじ)”という表現があります。昔の人が、その時期・その土地でできたものを食べるのが一番なのだ、として“旬”のものを美味しくいただく智恵を磨いてきたことに食の原点を見ることができるようですが、人の体と土とは切り離すことができないという発想が日本人の生命観の原点にあるように思われます。
冬には体を温めるものが、暑い夏には体を冷やすものが育つので、人間も季節に応じて自動的に体温が調整され、健康に生きることができるようになっているというわけです。
現代でも“旬”のものを美味しくいただくことが最高に贅沢な食生活となっているように思います。
ところが、自然界に存在するものが必ずしも安全であるとは限りません。毒性が強くて食べるとイノチにかかわる植物も存在するわけですから、長い年月をかけて試行錯誤を繰り返す中で人は自然界に適応してきたのです。
人々が長い間かけて築き上げた食習慣は地域社会で手に入る作物に限られていました。人が世界各地を飛びまわれるようになったのも、冷凍保存することのできる技術が確立したのもつい最近のことです。
人間生活のあらゆる分野で技術革新が進んだおかげで、ずいぶん便利になったのですが、良いことばかりではありません。この数十年の間に、加工食品の中に含まれる化学物質の弊害が無視できなくなって、私たちの健康に暗い影を投げかけるようになりました。
食生活のあまりの急速な変化に人間の体がついていくことができず、アトピーやアレルギー、喘息などの免疫にかかわる病気が蔓延しているのは周知の事実です。
これは人体の内部で起こった異変ですから、体外から薬を処方すれば解決するという問題ではありません。いま私たちは“自然に帰る”必要に迫られているのです。
“生命場”を育み、微生物と共生する
人間を“モノ”という立場からみてみますと、体の究極の原材料は素粒子ということになります。原材料としての素粒子が集まって原子になり、原子が集まって分子になり、分子が集まって細胞になり、細胞が集まってさまざまな器官になり、それぞれの器官が調和をとりながら独自の活動をしつつ全体を構成し、一つの体として機能しているのです。
最近の研究によりますと、半年もすれば体内のたんぱく質は全部入れ替わるということが分っています。肝臓などの器官はもっと早く、どんどん新しい細胞にとって代わられているのだそうです。
古い細胞は、時々刻々、新しい細胞に入れ替わっているとするなら、半年もすれば、ほとんどの病気が治ってしまうということになりますが、世の中には慢性病で悩んでいる人が多勢おられます。一体どうなっているのでしょうか?
この謎を解いたのが、イエール大学のハロルド・サクストン・バー博士です。バー博士の研究によって、肉体には“生命場”という目に見えない「場」があって、これが鋳型(いがた)の役割を果たしているということが究明されたのです。“生命場”という鋳型を通して肉体が形成されるので、原材料がどのように変化しようが、肉体は鋳型どおりになるというわけです。
プラスティック容器の製造現場をイメージしてみてください。加熱して液状になった樹脂を金型に流し込み、次にそれを室温にまで冷却して金型から取り出すと容器が出来上がります。
出来上がった容器の形状が歪んでいたとしたら、その原因は原材料にあるのではなく金型にあるのですから、正常な容器を作ろうとするなら、容器に手を加えるのではなく、金型を修正する必要があるということになります。
時々刻々、人の肉体は更新されているのにもかかわらず、もとの姿を保っていることが出来るのは、金型の役割をする“生命場”が存在していて、それが正常に機能しているからだということが明らかにされたのです。さらにバー博士の研究によって、“生命場”は宇宙の構成要素の一つであって、宇宙の法則に組み込まれたものであるということ、そして電気的に計測できるということが明らかにされました。
もちろん人間のことですから、プラスティック容器のように単純ではありませんが、元気に生きていくためには、“生命場”を正常に保つための注意が必要ということになります。
もっとも大切なことは「人の思い」なのだと思います。人は宇宙の構成要素のひとつですが、地球上に最後に登場した進化の頂点に立つ存在でもあります。「自然の摂理」に反する思いを続けていると“生命場”が歪んでくるので、健康に異常をきたすのみならず、周囲の環境もゆがんできて、その影響は動植物にも及ぶことになります。
“生命場”を正常に保つ上で、次に大切な要素は食べ物です。人間は何百万年もかけて自然に適応してきた生物なのですから、自然界にない不自然な加工食品を食べ続けていると、体内常在菌との共生関係が失われ、“生命場”のゆがみにつながると考えられます。
不自然な加工食品を摂取し続けていると、中に含まれている化学物質が脳の関所としての脳関門を突破して脳内に進入し、精神の働きに微妙な影響を与える可能性があるという研究もあり、特に注意が必要です。
日本は自然に恵まれていて、発酵技術が進んだ世界に誇る発酵王国です。人々は天然の発酵食品を食べることによって、微生物を体内に取り入れる智恵を育んできました。
微生物と共生することは、自然の摂理にふさわしい“生命場”を育む大切な要素です。
家庭料理に天然の発酵食品を取り入れることが必須の時代を、いま生きているといえそうです。
(つづく)
【参考文献】
河村文雄『人類の命を救う手作り酵素』(十勝均整社)
ハロルド・サクストン・バー『生命場の科学』(日本文教社)