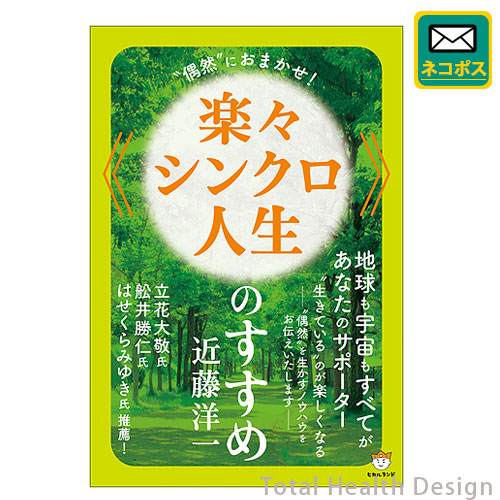2016年06月01日
コミュニティへの道(1)
私たちはいま、高度情報化社会の真っただ中を生きていると言ってよいと思います。
高度情報化というと、高度な情報が満ちあふれているような感じがいたしますが、現実を見てみますと、TVや電話、スマホなど、情報の伝達手段が高度だということであって、流れている情報が必ずしも高度ではないということに気づかされます。
情報という言葉は、明治になるまで日本には存在していなかったのだそうですが、森鴎外が英語のInformation,Intelligenceを翻訳することによって生まれたと言われています。
現代社会には、パソコンやスマホなどの情報機器を通してさまざまな情報が飛び交っていますが、そこに流れる情報の多くは五感を通して伝わってくるナマの情報ではなく、誰かの手によって加工された情報ですね。
元花園大学学長・盛永宗興老師は「ある程度自分で情報を制限し、大切なものをピックアップして静かな中で大切なものをしみじみと受け取っていく。どんなにごちそうがたくさん並べられていても、自分の好みに合わせて選び出して、数少ないものをよく味わって食べる。そのような生き方がもういっぺん見直される時代になったのではないかと思う」として、大学生に向けて次のように話しておられます。
森繁久弥さんが、ある雑誌で話していたことをこれからちょっと申しましょう。彼の友人のある会社の社長が、地域のロータリークラブの会長に選ばれたとき、ホテルの披露宴で皆に赤飯を出しました。ホテルで赤飯というのは珍しいことですが、彼はその時、次のようなスピーチをしたそうです。
自分は長野県の貧しい農家の長男坊として生まれた。少し成長してくると、この程度の広さの田畑では、いくら頑張って働いても、食べていくのが精いっぱいで、年老いていく親に楽をしてもらうことも、弟や妹たちに満足のいく教育を受けさせることもできないということがわかってきた。
そこでそういう状態を打開するためには、都会に出て働かねばならないという結論になったのですが、戦前のことです。跡取り息子が先祖伝来の田畑を放り出して出ていくことを悲しまない親はいない。親の悲しみが目に見えるから、どうしても口に出して言い出せない。
そういうことでとつおいつ(※)悩んだ末、とうとう覚悟を決めて、ある晩自分の貧しい下着類を風呂敷に包んで、母親が起きる前に朝早く、家出をしようとしました。(※あれこれ思い迷うさま)
ところが、台所の土間から裏口を通って出ようとすると、いつもは寝ているはずの早朝に母親が台所で仕事をしている。そして振り向こうともせずに、出ていく息子に向かって「赤飯を炊いておいたから食べていけ」と言ったそうです。
本当に立ちすくんでしまって動けない。見ると狭い台所の横の卓袱台に赤飯が盛ってある。引きずられるような感じでそこに座ると、母親が炊きたての味噌汁を添えてくれた。
しかし食べようと思っても、のどのあたりに涙の塊のようなものがつかえていて、口に入れてもどうしてもその赤飯が呑み込めない。その様子を見た母親が「起きたばかりで食欲がないのなら、握り飯にしてやるから持って行け」と言って、赤飯を握り飯にして渡してくれたのだそうです。
それを持って暗い外へ逃げるように飛び出したのですが、自分の家出を引きとめもせず、説教もせず、怒ることもせず、黙って赤飯の握り飯を渡して送り出してくれた母親が、その後、きっと台所の流しの端につかまって泣いているであろう姿が、目に浮かんで、彼もまた遠い停車場まで泣きながら歩いて行ったのだそうです。
そして都会に出て働いて、ある程度のお金や時間、地位が得られても、お母さんから渡された赤飯が心の中にいつまでも残り、ひとつのお守りのようになって、今日まで脇道へ行かないですんだ。
そして、今、あなた方のような立派な人々の集まりの中で、会長という名誉な位置につかせてもらうまでになった。だから今日はどうしても、その思い出の赤飯を皆様に食べていただきたいのだ、と話されたというのですね。
森繁さんというのは大変な感激家のようでありまして、この対談の間、涙を流しながらこの話をされたようでありますが、私も本を読んでおって思わずもらい泣きをしました。
(盛永宗興:季刊『禅文化134号』(1989)より引用させていただきました。)
情報化からコミュニティへ
“子どもを大切に育てる”様を“手塩にかける”と表現しますね。お母さんが手のひらにお塩をつけて握ってくれたおにぎりは、ことのほか美味しいのではないでしょうか?
手のひらのことを掌(たなごころ)と言いますように、手のひらには、愛に満ちあふれた心が宿っているという実感を誰もが持っていると言ってよいと思います。
またお母さんの掌には発酵菌が宿っていて、お母さんの分身としての微生物が塩と一体となって、おにぎりを格別の発酵状態にもっていってくれるのだと思います。そのおにぎりをいただく人の感謝の心とお母さんの心が共鳴すると、ますます美味しさがつのるのでしょう。
おにぎりのことを“御結び”と言いますが、心と心を結んでくれる働きを表現していて、日本語の奥深さが感じられるのではないでしょうか?
人類は、狩猟社会、農耕社会、工業社会を経て情報化社会へと進化し、そして今、高度情報化社会の真っただ中を生きている、その一方で人心の荒廃と自然環境の崩壊という深刻な課題を抱え込んでいるのが実態だと言ってよいと思います。
いま私たちに必要なのは、高度な情報機器によって伝えられる、誰かの手によって“加工された情報”ではなく、生身の人間同士の交流を通して得られる“ナマ情報”なのではないでしょうか?
盛永宗興老師は、さらに
「私たちが、テレビやラジオなどを通じて得ている情報は、すべて誰かの頭や心で分析され、選別されたものなのです。これに比べてこのお母さんは、つねに自分の子どもに対しては、生の情報をもっていた、心の底までしみじみとした子どもの情報をもっていた。…だからこのお母さんは、話をしなくても自分の息子が何を考え、そしていつどのようなことを実行するかを的確に知っていたのです」
と述べておられます。
“ナマ情報”が生身の人間の心の中でじっくり発酵し、さらなる価値を生むことによって人間は進化すると言ってよいと思います。
醍醐味
ものごとの深い真髄を表現するとき、“醍醐味”という言葉が使われます。
奈良時代、乳牛の飼育をしていた人々は、牛や羊のお乳から、さまざまな製品を創りだしていたと言われています。
お乳すなわち“乳味”から出発して、“酪味”、“生酥味”“熟酥味”そして“醍醐味”に至る5段階発酵のことが興味深く伝えられています。
“醍醐味”というのは、純粋なヨーグルトのような味、転じて最高の味わいを指す言葉として使われていました。奈良時代や平安時代の人々は、そんな貴重品を味わっていたようなのです。“醍醐”というのは、仏教の経典の進化を表していて、進化した最終形態が「大涅槃経」であり、“醍醐”は仏の最高の教えを指す言葉だと言われています。
情報化が極限にまで進展した今、次にやってくる社会はお互い同士“ナマの情報”を楽しみ合う「コミュニティ(共同体)」がテーマになるのではないでしょうか?