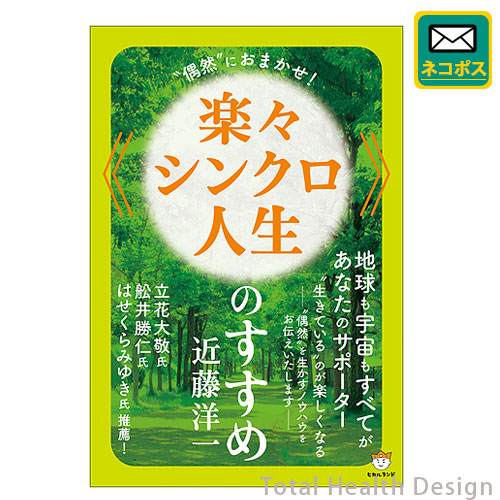2020年06月01日
因果律と共時性
戦後に生きる私たちは、学校で、いわゆる“科学教育”を受けて現在に至っています。
私たちが日常生活において体験するどのような現象も、「原因があって結果が生じる」すなわち時間が経過するとともに現象が変化していく過程がテーマとなっているのではないでしょうか?
私たちの日常生活は、時間の経過に注目して、因果的に現実をとらえようとする『因果律』によって構築されているのが、常の姿だと言ってよいと思います。
金子みすずさんの詩『海とかもめ』をご紹介させていただきます。
海は青いとおもってた、
かもめは白いと思ってた。
だのに、今見る、この海も、
かもめの翅(はね)も、ねずみ色。
みな知ってるとおもってた、
だけどもそれはうそでした。
空は青いと知ってます、
雪は白いと知ってます。
みんな見てます、知ってます、
けれどもそれもうそかしら。
因果律を超えて、空間的にへだたった二つ以上のものの間に、同時に同調現象が起こることがあるものです。
ずいぶん前のことですが、私たちが仕事をしている職場の前に、道路をはさんで神社がありました。ある時、知人のU(仮名)さんが執筆された小説が芥川賞の候補に選ばれました。職場の2階の窓から、Uさんのことをイメージしながら、ぼーっと神社を眺めていると、車体に「U」という名を書いたトラックが通り過ぎていきました。Uというのは、ありふれた名前ではないものですからびっくりいたしました。
しばらくして家に用事を思い出し電話をしようと思ったところ、知人のMさんが新車に乗ってやってきました。車番を見ると、何と!我が家の電話番号と同じだったのには、またまたびっくりです。どうしてこのようなことが起こるのか、さっぱりわかりませんが、同調現象を引き起こすような“作用の場”としての空間が存在しているということになるのではないでしょうか?
そのような空間には、何らかのエネルギーが流れ働いていると中国人は考えたと言われています。『気』ですね。
古代の中国人は、大宇宙の中に、同時同調現象を引き起こすエネルギーの流れが存在することに着目したというわけです。宇宙空間に存在する事物相互の間に張り巡らされた見えない作用を念頭におき、世界を観察した結果、『共時的思考』が生まれたと考えられます。
心理学者のユングは、西洋科学の基本的な思考形式である『因果律』に対比される原理として、『共時性(シンクロニシティ)』という言葉で、その原理を科学的に表現したと考えられています。
西洋的な思考においては、自然に対して「何故そうなった」「これからどうなる」といった感覚で、創造から終末まで「時間の流れ」の中で『WHY?』が問われる“因果的思考”が主流であるのに対し、東洋的な思考においては、「世界の始まりも終わりも問わない。世界はどのように動いているのか・・・『HOW?』が問題」すなわち時間より空間が問われる“共時的思考”が顕著になるようです。
身体を場として、心理作用と生理作用が、因果関係としてではなく、同時同調的な関係で成り立っているというのが、東洋的な医療のベースとなる身体観と言えるのではないでしょうか?
空間に存在する事物相互の間に張り巡らされた見えない作用に即して世界を見るというわけです。「気」が主役を務めていることになります。「気」が全身にくまなく流れ、エネルギーを供給していくための基本構造として『経絡』のネットワークがあるというわけです。
この流れが停滞すると、心身の異常が発生することになります。
鍼治療は、『経絡』に沿って存在する『経穴』(ツボ)に刺激を与えることによって、「気の流れ」が順調になり、元気が回復するというメカニズムが働いているように思われます。
「気の流れ」は無意識の領域に属していて、感覚や顕微鏡によってその存在を確認できないだけに、21世紀に残された大切なテーマになるのではないでしょうか?
西洋の科学は、時間の経過に着目し、あらゆる現象を原因と結果という観点からとらえようとしたのに対し、中国では、空間に張り巡らされた見えない力に着目し、世界を観察したと考えられています。このようにして因果的思考と共時的思考が生まれたというわけです。西洋的な医療においては、身体全体を診察することによって、まず病気に名前をつけることから出発し、その原因を考え、それを除去する方法を考えていく、いわば攻撃型の治療という気がいたします。
一方、東洋的な医療においては、個々の器官の因果関係を基本として身体の状態を見るのではなく、気の流れの異常など、身体全体としてのアンバランスを観察することが基本となっているのですね。
東洋医療の診断では、病気に名前をつけるよりも治療の方法を明確にするという実際的な目的が先行しているのだそうです。
生体の気のアンバランスを回復し、身体内部にある自然治癒力を活性化することによって、自然に健康が回復されるところに、注意は向けられていると言われています。
気の流れは経絡に沿った多くの経穴(ツボ)を通して体外に流出あるいは流入していると考えられているそうです。「気」は宇宙にみなぎっている生命エネルギーと考えられていますので、環境との相関関係から切り離して身体のメカニズムを考えることはできないということになります。身体を環境から切り離さず、身体を開放系としてとらえているわけです。
気の運動を基本におくことによって、心理―生理―物理(精神―生命―物質)という三つの次元を通して、人間と自然の関係を主体的身体に即して見る、という一貫した見方に至るというのです。
参考文献:
*湯浅泰雄『身体の宇宙性』岩波書店(2012年)
【お知らせ】
いつもご愛読いただき、ありがとうございます。今月号の掲載をもちまして、「バンクシアの響き」の連載をしばらくお休みさせていただきます。