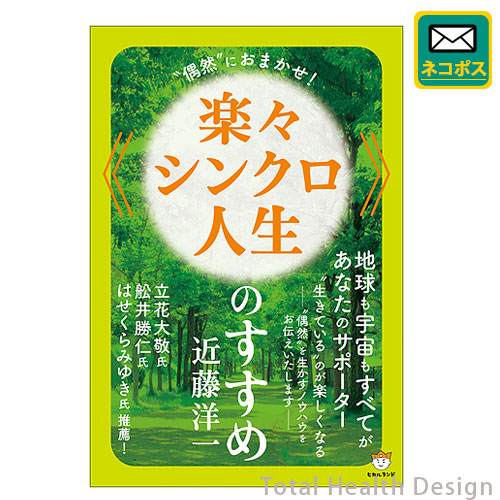2013年04月01日
4月 つながり(1)
2012年に生まれた子どもの名前で一番多かったのが、男の子は“蓮”、女の子は“結衣”だったそうです。お寺の池などに咲いている蓮の花は、一つひとつがそれぞれ別々のイノチをもっているかのように見えますが、その茎は一つの蓮根につながっています。蓮の花は、一つのイノチを共有しているのです。
女の子の“結衣”はどうでしょうか?天女は特別の羽衣を身につけると伝えられていますが、“結衣”という名前からは、天女のように美しい衣を身につけさせてあげたいという両親の切なる願いが感じられるのではないでしょうか?
2011年の3.11大震災の際に、“絆”という言葉が脚光を浴びたのは記憶に新しいところですが、人々の心の中に、お互いに“つながりたい”という願望が芽生えているのを感じますね。何かと波乱含みの2013年ですが、多くの人が“つながり”を求めている背景には、お互いつながっていないのではないかと不安に感じる現実があるからなのかも知れません。
もうずいぶん前の話ですが、「日本人とユダヤ人」(イザヤ・ベンダサン著)という本がベストセラーとして話題を呼んだことがありました。その本で著者は、ユダヤ人が創造性豊かで個性的な人種であるのに対し「日本人は隣百姓である」と論じていたように記憶しています。
農耕民族である日本人は、隣の人が草を刈るとそれを真似して草を刈り、苗を植えているのを見ると自分も苗を植えるという風に、なんでも人の真似をしたがる民族であるという趣旨だったように思います。
その昔、日本の田舎には「村八分(むらはちぶ)」という言葉があって、時には仲間はずれにされることもあったようなのですが、それでも葬式や火事の時などは、協力して助けてあげるというしきたりがあったと伝えられています。
1960年頃までは、都会でも「向こう三軒両隣」という言葉が健在でした。近所同士仲良く生活するという風習が多くの人の間で共有されていたように思います。
“つながり”を大切にしていたはずの民族の“つながり”が希薄になってしまったように感じられる昨今ですが、いま何が起こっているのでしょうか?
科学思考と“つながり”
戦後、私たちは日進月歩の科学技術の恩恵にあずかり、心ゆくまで便利で快適な生活を謳歌してきたといってよいと思います。科学万能、便利で至れり尽くせりの世の中になりましたが、何事も良いことばかりではありません。
科学というと誰か特別な人がするものという感覚があって、他人事のようですが、私たちの生活を支えている価値観、すなわち私たちの常識は、小学校から大学にいたるまで一貫してなされている科学教育に基礎をおいて形成されています。
科学は自然を認識する認識概念であり、科学者の役割は新しい概念を生み出すことです。自然を極限にまで細分化することで科学は発達してきました。科学が発達し、細かいことがわかればわかるほど、専門家でなければどうにもならないということになってしまいます。科学は「切り離す力」が強力なのです。私たちの頭脳が科学的になればなるほど、私たちの生活の根底にあって、お互い同士を結び付けてくれていた根っこが見えなくなっていくわけです。
たとえば科学が発達したおかげで、人間の体についてもいろんなことがわかるようになりました。
体 → 器 官 → 細 胞 → 分 子 → 原 子 → 素粒子…と体を極限にまで細分化し、もうこれ以上分割することのできない量子の世界にまで辿りついたのです。体を構成する分子や原子、素粒子をいくら分析しても体のことはわかりませんし、心のこともイノチのことも見えてこないと言ってよいと思います。
細部のことが明らかになればなるほど、病気で苦しむ人が増えて、医療費が増大するというのが現実の姿です。呼吸器と消化器、脳の細胞と胃の細胞、窒素分子と酸素原子など、体を構成する要素の“つながり”が見えてこないのです。
「切り離す力」の強い科学が発達すればするほど、人と人のつながりも希薄になる傾向があるようにも思われます。
かつての日本では古事記、日本書紀を通して神話が継承され、物語を共有することで、お互いの“つながり”が維持されていたのですが、戦後、科学思考一辺倒の世相の陰で、これらの神話が顧みられなくなり、“つながり”も弱くなって現在に至っています。
「神話をなくした民族はやがて命を喪失する」と言われていますが、まさに危機に瀕している日本の現実を表現しているようでもあります。科学技術の粋を尽くして形成された都市空間で、切り離す力が強力な科学思考にひたりきっていると、人と人との間の“つながり”も切れてしまいかねません。
農耕民族としての日本人は格別に“つながり”を大切にしてきた民族だといってよいと思います。日本人が愛し、親しんできた国歌、俳句、童謡をはじめ、あらゆる物語の中心にあるテーマは“つながり”なのです。
君が代
君が代は
千代に八千代に
細石の巌となりて
苔のむすまで
砂のような小さい石がやがて大きな巌になり、一面に苔が生い茂る―日本という国は千年も万年も幾世代にもわたって、自然の摂理に従って生々発展し続けるのだという基本理念が謳われています。
民族の基本理念としてのたて糸が世代を超えて途切れることなくつながり、 自然の摂理に則って中心軸としての機能を果たしていることが、国としての安定性につながるのだと思います。日本の国がいま必要としていることは科学思考もさることながら、「このような国にしたい」という切なる願いを皆で共有することだと思われます。
松尾芭蕉
閑さや 岩にしみ入る 蝉の声
蝉と岩とはまったく別々の姿をしているにもかかわらず、心を澄ませると深いところで、お互いにつながっていることが謳われています。そこには、科学思考からは見えてこない日本独特の深い情緒が感じられるのではないでしょうか?
金子みすゞ
≪花のたましい≫
散ったお花のたましいは、
み佛さまの花ぞのに、
ひとつ残らずうまれるの。
だって、お花はやさしくて、
おてんとさまが呼ぶときに、
ぱっとひらいて、ほほえんで、
蝶々にあまい蜜をやり、
人にゃ匂いをみなくれて、
風がおいでとよぶときに、
やはりすなおについてゆき、
なきがらさえも、ままごとの
御飯になってくれるから。
金子みすゞの詩が多くの人に愛されているのは、生と死を超えてつながる自然界の営みに心を打たれるからなのだと 思われます。いま、日本人に必要なことは語り継ぐべき「物語」を共有することではないでしょうか? (つづく)