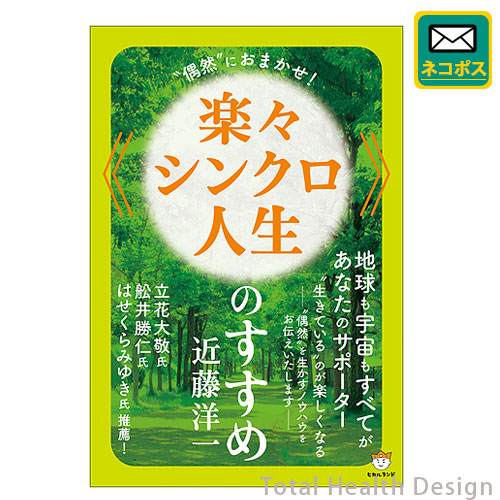2018年04月01日
「イヤシロチ(良い場)」を創る
子どもの頃、トランプや花札などの遊びを通して「場」という言葉になじんでいたせいか、日常生活で「場」という言葉を何げなく、頻繁に使っていたように思います。
花札では、「場6に手7」という表現がありました。自分の「手」の内に7枚の札が配られ、他の人との共通の「場」に6枚の札が配られ、“自分だけの世界としての「手」”と“他の人と共有する世界としての「場」”とを考慮しつつ生きていく知恵が、知らず知らずのうちに遊びを通して身についたように思います。以下、「場」について考えてみることにいたします。
カタカムナの智慧
満州鉄道という会社が中国各地の鉄工所で、鉄製品を製造していた時のことです。すべての工場で同一規格に基づいた同一の方法で鉄製品を製造していたのですが、どういう訳か、良好な鉄製品ができる工場のある一方で、すぐに錆びが出る製品しかできない工場があったのだそうです。
当時、陸軍製鉄技術研究所所長をしていた天才物理学者・楢崎皐月氏は、その原因は工場の"【場】の良し悪し"にあるということを突き止められたのでした。
楢崎氏は、物理や電気、化学など幅広い分野を学び、20代で特殊絶縁油を発明。戦時中には人造石油を発明して軍が採用するなど、若いころから天才的な能力を発揮しておられました。
そしてケカレチ(気枯地)すなわち酸化環境にある工場でできた鉄製品は錆びやすいのに対し、マイナスイオンの豊富なイヤシロチ(弥盛地)すなわち還元環境にある工場でできた製品は錆びにくいということを突き止められたのでした。
【場】の良い土地(イヤシロチ)そして【場】の悪い土地(ケカレチ)のルーツは、今から1万年以上前の旧石器時代に存在していたと言われる「カタカムナ文献」にありました。
このカタカムナ文献を解読したのが、楢崎皐月氏です。
カタカムナ文献には、現代科学に匹敵するような知恵や技術が体系化してまとめられていて、現代科学の概念を超える宇宙の仕組や世の中の構造までもが記されていることが明らかになっているそうです。
楢崎氏はカタカムナ文献をもとに科学的な研究を進め、その知恵を解読し、独自の視点で体系化されたのでした。
終戦後は、焼け野原の土地改良のため、日本全国一万二千カ所の土地の還元電圧と電流の向きを調査し、植物の優勢生育地と劣性生育地の関連を突き止め、報告されました。
その報告によって、地球上に存在する電気の分布状態は一様ではなく、そこに行けば電子を豊富に受け取ることのできる還元電圧地帯(イヤシロチ)と、逆に電子を奪われる酸化電圧地帯(ケカレチ)があるということが解明されたのでした。
アマウツシ
カタカムナ文献によりますと、上古代の人は、宇宙や自然を創りだした根源的なエネルギーを「アマ」と表現し、それが元になって万物が構成されていると認識していました。
この宇宙に存在する根源的なエネルギー「アマ」を地上に移す働きが「アマウツシ」です。
イヤシロチとは、アマが豊かに満ち、その場に身をおくと生命力が旺盛になり、身体は元気に、心は前向きに働く環境、ということになります。
電子(マイナスイオン)が豊富に供給されるイヤシロチでは、植物がよく生い茂り、置いてあるものも長持ちすることが経験的に知られています。そんなところは住み心地が良いので、人はイキイキと健康になります。
また、事故も起こりにくい、女性なら美人になる、商売をすると繁盛する、といった調子で、豊かな日々を送ることができるわけです。
一方、ケカレチでは電子が奪われるため、植物の生育が悪く、置いてある物も劣化しやすく、事故がよく起こるなど住み心地も悪くなると言われています。商売をするとうまくいかなかったり、病気になったり、事故が起こったりなどのトラブルが起こりやすくなるというわけです。
「場」がもっている力が、人の健康管理や、住環境、農作物づくり、そして幸運・不運の左右などにまで、大きく影響していることがわかります。
このように、楢崎氏は、実践科学と古代の叡智の探求の両面から、土地改良法を見出されました。それを基礎として様々なイヤシロチ化技術が開発され、今日に至っています。
日本語には、【天然】と【自然】という二つの言葉がありますが、その区分は明確ではありません。
楢崎皐月氏によりますと、【天然】は「自然理の支配する宇宙現象の範疇には入らない。宇宙における現象背後の世界を天然界と言い、自然理の支配する有限宇宙を、その内にかかえている。すなわち人間の五感ではわかり得ないが実在している」という世界です。
【天然】というと、ともすれば神秘思想となって、【天然】と【自然】を混同したまま、物事を考えるのが現代人の習性になっている、と楢崎氏は指摘しておられます。
住み心地の良い「イヤシロチ」という【場】、住み心地の悪い「ケカレチ」という【場】は一般的な言葉として使われていますが、【モノ】ではありませんね。
戦後の学校教育は、【モノ】中心の唯物論を前提として組み立てられていますので、【天然】と【自然】、そして【生命】を理解するには不十分なのかもしれません。
コミュニティへの道
このように述べてまいりますと、「場」という言葉は、「土地のあり方」というニュアンスが強く感じられるようですが、土地だけに限った概念ではありません。
「場」というのは、ある物理的な量が、ある空間に連続して分布している状態を指しています。電気の場合は「電場」、磁気の場合は「磁場」、重力の場合は「重力場」となります。
……私たちの体は60兆の細胞でできていて、肝臓や心臓などの臓器を形成しています。さらに身体全体には、血液やリンパ液が流れていて、その背景には【気】が満
ち満ちています。……一つ一つの細胞を包み込んで身体全体に流れる「イノチの流れ」、それが「場」なのですね。
私たちの肉体は様々な細胞が、お互いもちつもたれつ、自分自身を形成しながら、ともに存在し、コミュニティを形成しています。コミュニティ的存在なのです。
ところがガン細胞は、「俺が、俺が…」と自己意識が強くて、多様な個がともに生きていくというコミュニティ的存在の形がとれません。
「生きる」ということは、「生かされている」ということでもあるわけです。
このように考えてきますと、私たちは親元である自然界にどのようにお返しをしていくのか、が問われているということを強く感じさせられるのではないでしょうか?
地球上に存在しているものを「もの」として見るのではなく、「イノチの働き」という観点から見ることが問われているのですね。
参考文献:
・相似象学会誌『相似象』相似象学会事務所
・THDイヤシロチ研究会『“生命”が活性化するイヤシロチ』トータルヘルスデザイン